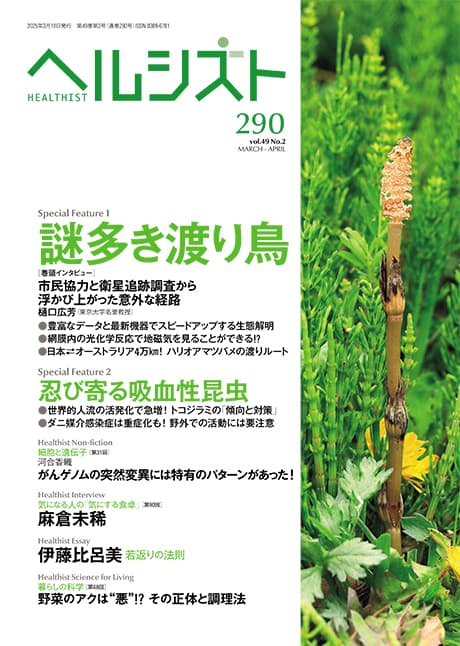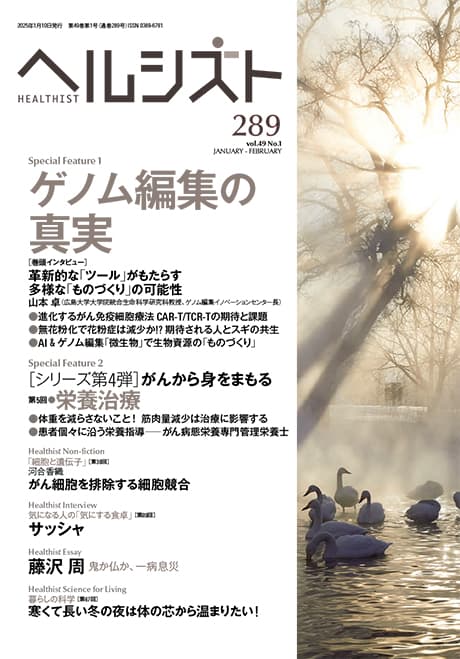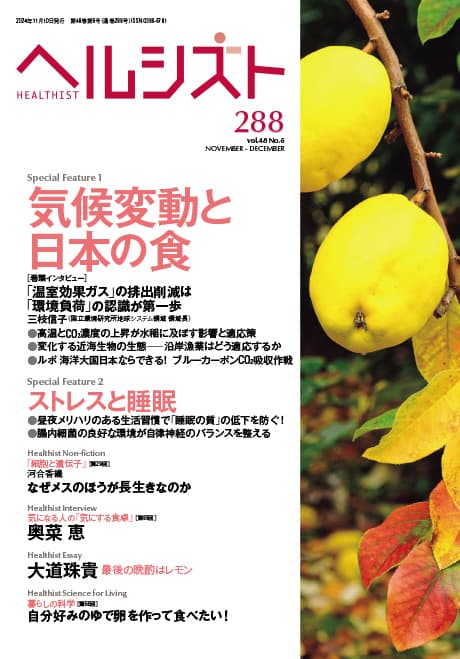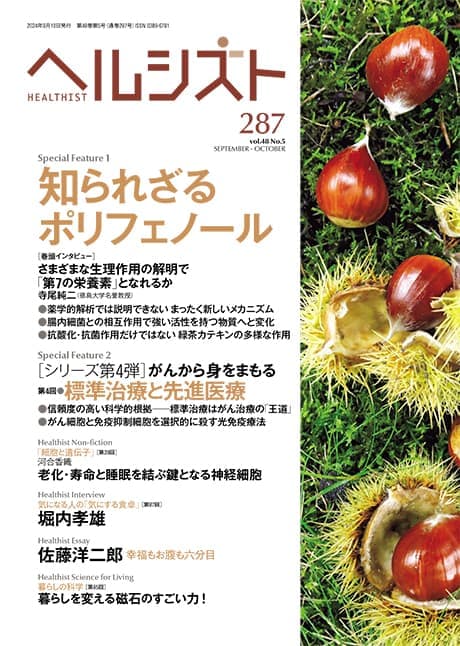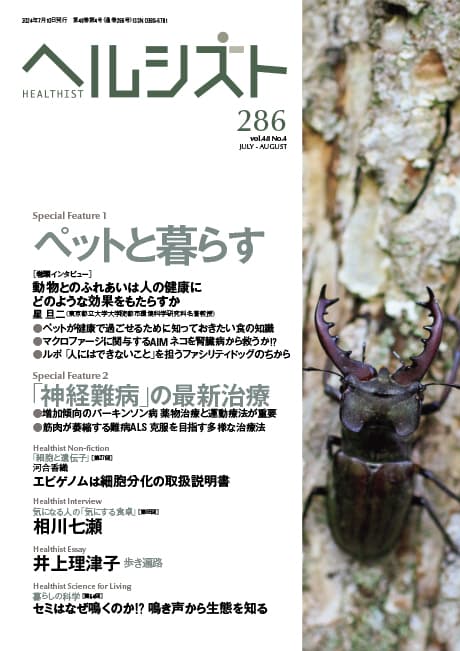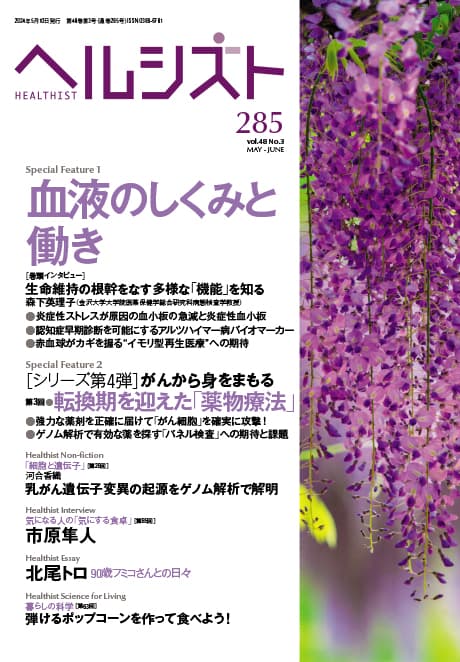生命と真摯に向き合う
《初めはごく単純な一つの生き物に吹き込まれた生命は、やがてとても美しく、とても素晴らしい数えきれない形に変化してきた。そして、それは今も続いているのだ》
これは、「進化論」の開祖である19世紀英国の博物学者チャールズ・ダーウィン(1809〜1882年)が、1859年に著した『種の起源』の末尾に記した一節ですが、この一篇で説いた「進化」の概念は、生物学のみならず、後の社会にも大きな影響を与えたといわれています。というのも、それは、合理的な考え方が広まった産業革命後でも多くの人が信じて疑わなかった、「生物の種は神によって創られた」という世界観を覆すものだったからです。
その「進化論」につながる礎となったのは、ダーウィンが20代の5年間を英国海軍の調査船ビーグル号に博物学者として乗船、南米大陸沿岸からガラパゴス諸島、ニュージーランド、南アフリカなどを回り多様な生物を観察したことでした。そして「種は変わらない」とする、それまでの理論がそぐわないと気付いたのです。
後に『ビーグル号航海記』として出版された、その研究日誌は、大変詳細な観察記録であるのに驚きますが、ダーウィンはそれからさらに20年という歳月をかけ、世界各地の研究者たちと、多いときには年に500通にも及ぶ手紙をやり取りして、研究と緻密な検証を重ね、膨大な考察を経て自らの考えを発表したのです。
ダーウィンの研究日誌は生き生きとし、何より出会った生物(肌の色や習俗の違う人々も含め)への純粋な関心と、分け隔てのない視線、そして敬意が感じられて心惹かれます。
それまで社会、そして自らを支えてきたものへ異を唱える重さや恐れは、いかばかりだったでしょう。疑問に目を背けず、向き合い続けて発表までたどり着いたのは、生命というものへ真摯に向き合う姿勢があったからこそだと思うのです。
現代の生物学は、「生物の種は神によって創られた」という概念を否定したダーウィンの『種の起源』を起点に大きく進化し、遺伝子情報の解析から分子レベルで生命現象を解明する分子生物学の登場により、これまで不明だった多くのメカニズムや物質の構造が明らかにされています。
しかし渡り鳥はなぜ迷わず目的地にたどり着くことができるのか―という疑問はいまだに確かな解答を得られていないのです。この問いにはいくつかの仮説があり、渡り鳥の体内にあるマグネタイト(磁気微粒子)が棒磁石型磁気コンパスのように働いて方位を感知しているのではないかという、「マグネタイト仮説」が有力視されてきました。しかし量子生命科学と呼ばれる分野で、「ラジカル対機構説」という仮説が提唱され、新たな角度からの解明が進んでいます。
ラジカル対とは、核の周りをペアで周回している電子が熱や光などの強いエネルギーによって1つだけの分子(ラジカル分子)となり、それがほぼ隣り合わせで存在する状態のことです。ラジカル分子は電子スピン(電子の自転)によって磁石としての性質を有しており、ラジカル対になることで電子スピンの状態は複雑に変化して地磁気コンパスのように作用し、その結果、なんらかの反応を起こすことが分かってきました。
ラジカル対機構説では、鳥の網膜内に存在する、青色光に反応するクリプトクロムという光受容体タンパク質がラジカル分子として働いてシグナルを脳に送ることで、鳥は地磁気を視覚的に感知、つまり見ているのではないかと推論しています。
量子生命科学は、量子力学の視点で分子機能を追究し、生命の原理を解き明かす、量子力学・量子科学技術と分子生物学を掛け合わせた新しい学問で、次世代ポストゲノム研究の主流として注目されています。量子力学的な手法で進んでいる渡り鳥の研究はやがて、生体分子構造の根本的解明につながるに違いありません。
『種の起源』から160年余り、科学はどこまで生命進化の謎に迫っているのでしょうか。