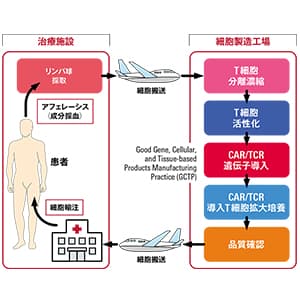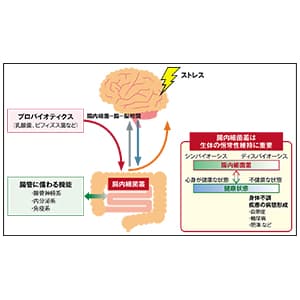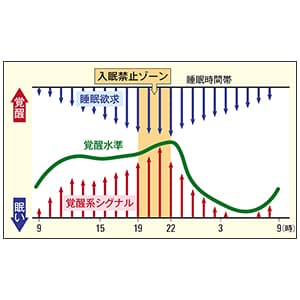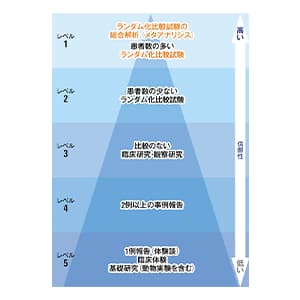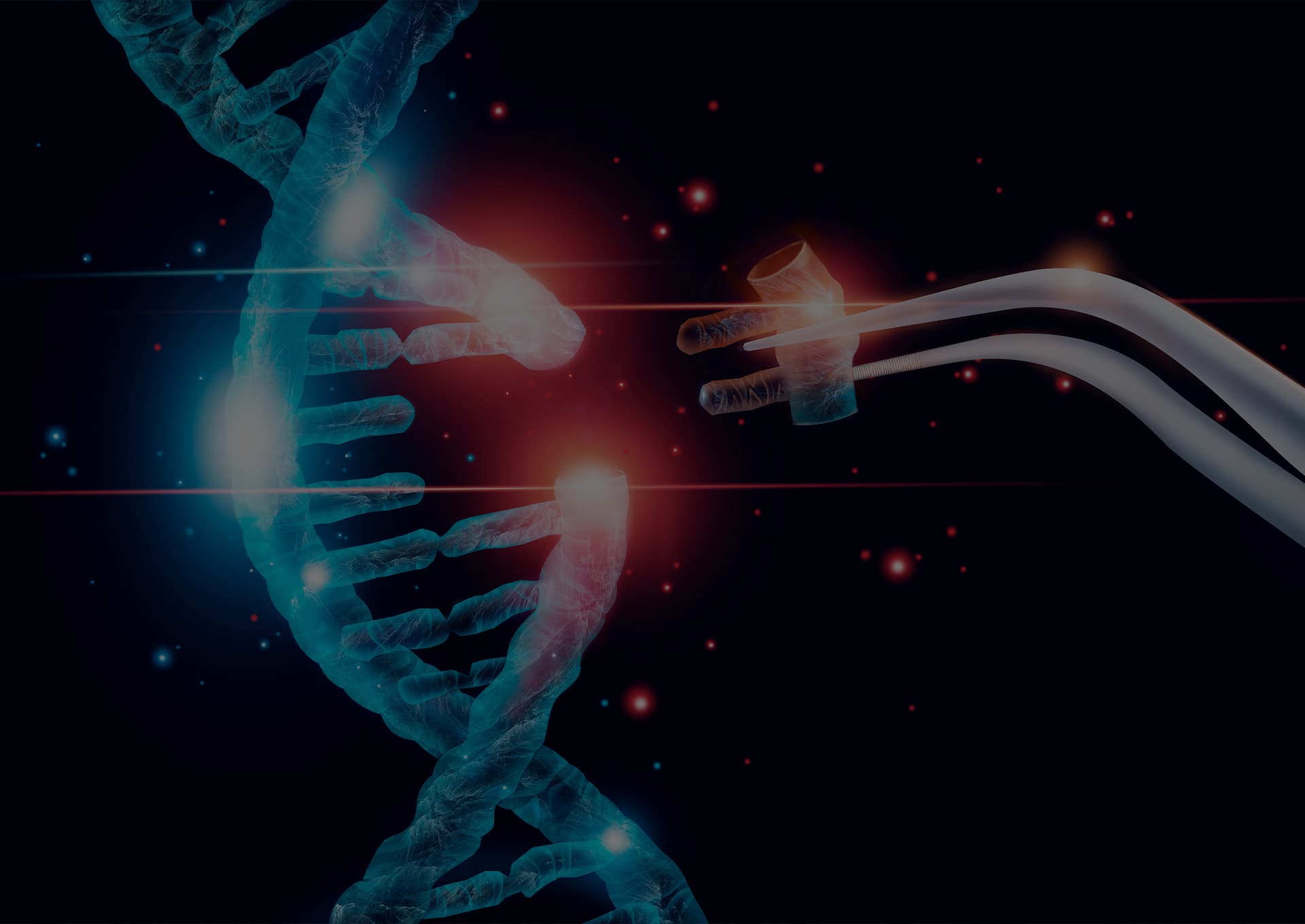〈シリーズ〉がんから身をまもる
第6回 緩和ケア 診断された時点から始まる あらゆる苦痛に対処する医療
緩和ケアと聞くとがんの痛みを軽減する治療が想起されるが、実は、「生命を脅かす病に関連する問題」、すなわち命に関わる病気に起因するさまざまな苦痛に対処する医療だ。対象は身体的な痛みをはじめとして不安や精神的なつらさ、経済的な問題など多岐にわたるが、やはりがんの痛みへの関心が一番高い。治療法が進化して治療期間が長くなり、治療と並行して緩和ケアを行うことも増加しているという。緩和ケアは誰もが受けられる、痛みや苦しみを和らげる確かな医療なのだ。