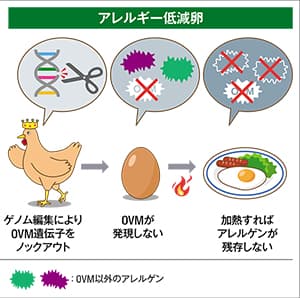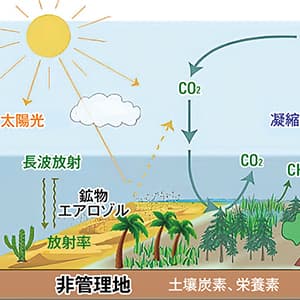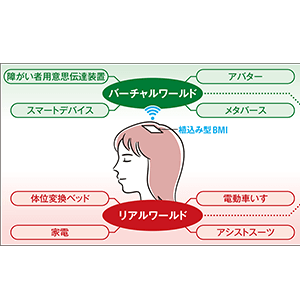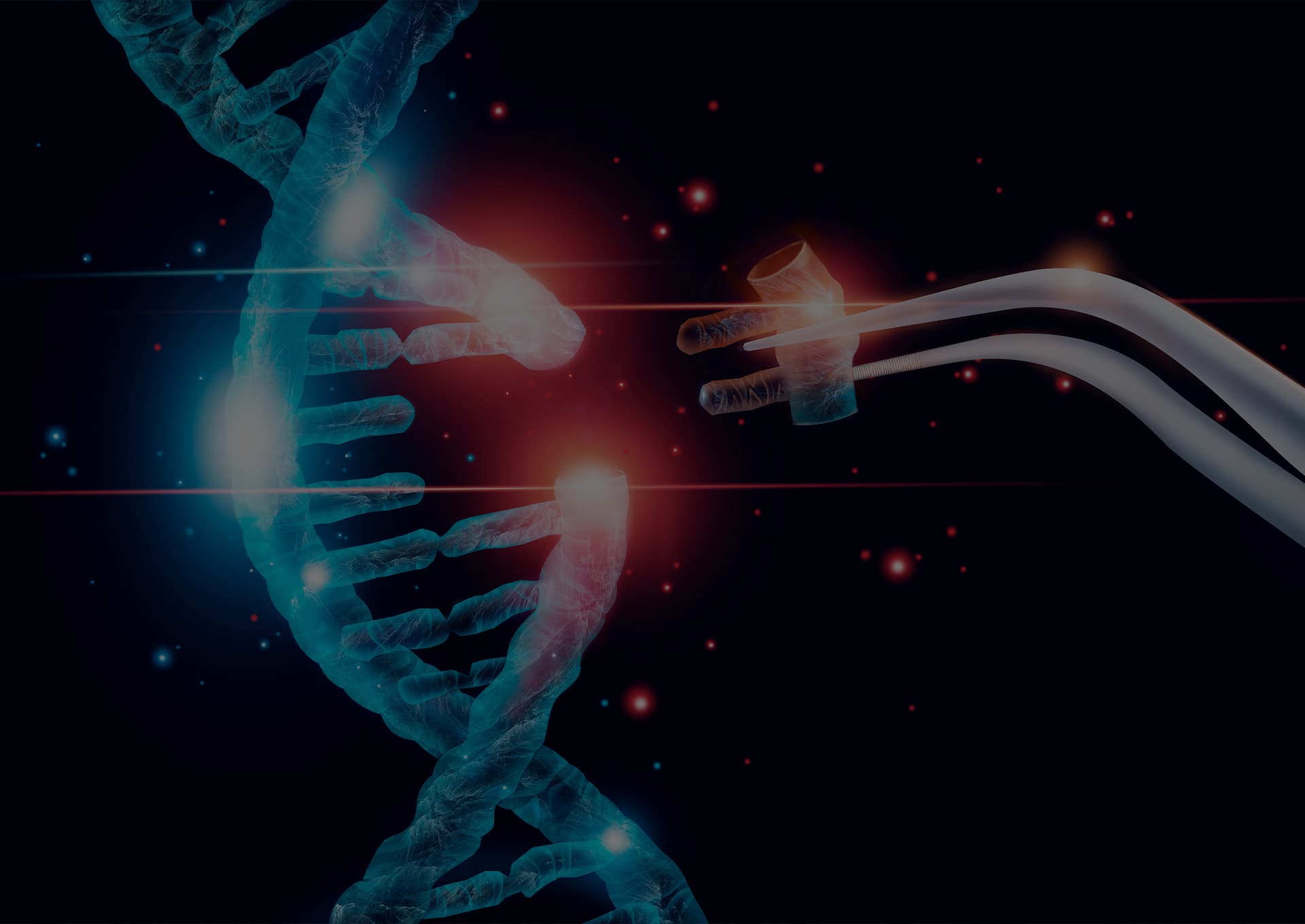特集 ゲノム編集の真実 無花粉化で花粉症は減少か⁉ 期待される人とスギの共生
日本で、ブタクサやスギ花粉を原因とするいわゆる花粉症が初めて報告されたのが、1960年代。以来、有病率は年々増加し、今や日本の「国民病」と呼ばれるようになった。なかでもスギ花粉症が最も多く、約4割の日本人がスギ花粉症に悩まされている。しかしスギは国土保全や生活に欠かせない資源のため、林野庁は花粉の少ない品種の開発に努めてきた。今では、ゲノム編集技術を用い、花粉をまったく出さない品種への改良が進んでいる。人とスギの共生が期待される。