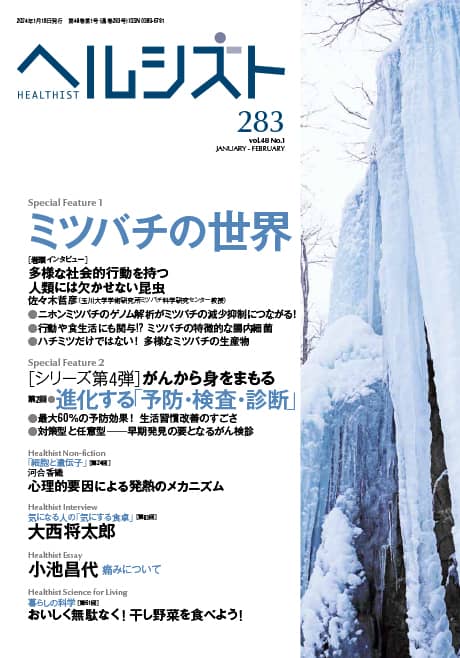リスクコミュニケーション
「看護とは、新鮮な空気、陽光、暖かさ、清潔さ、静かさなどを適切に整え、これらを活かして用いること、また食事内容を適切に選択し適切に与えること、こういったことのすべてを患者の生命力の消耗を最小にするように整えること」
新型コロナウイルス感染症の予防法として盛んに呼びかけられている「換気」ですが、いまから160年ほど前、フローレンス・ナイチンゲール(1820~1910年)が、その重要性を提唱していたことには改めて驚かされます。それは感染症の研究が始まる前で、日本はといえば幕末の、ようやく開国した頃のことでした。
ナイチンゲールは、英国の裕福な家庭に生まれ、幼少時より哲学、数学、天文学、歴史、地理、心理学、外国語、絵画や音楽など幅広い教育を受けて育ちました。看護職を志しますが、一躍その名を広めたクリミア戦争の従軍から帰ってからは体調を崩し、実践での経験は3年に満たなかったといわれています。しかしその後も自室から動けない状態のまま看護師訓練学校を開設し、看護や病院の制度、衛生や福祉について、政府や関係機関に対し膨大な提言をし続け、およそ150篇もの著作を執筆、国民の健康を実現する改革に努めました。的確な指摘を行うため統計学を取り入れていたのも画期的でした。
読み継がれている『看護覚え書』は、「他人の健康に責任を負っている人たちに考え方のヒントを与えたい」と書かれたもので、いまもって看護師のみならず、健康を望む私たちにとってとても参考となります。
東日本大震災、そして東京電力福島第一原発事故から10年、事故直後から放射線健康リスク管理アドバイザーとして被ばく医療や住民の健康管理に尽力した神谷研二広島大学副学長/福島県立医科大学副学長は、この原発事故は社会と科学のコミュニケーションのありように大きな教訓を残したと評する一方、日本にはリスクコミュニケーションという考え方が根づいておらず、「いくら正しい情報を提供しても伝わらないというジレンマがあった」と、振り返ります(〈「福島原発事故」から学んだ最も大切なものは信頼関係〉参照)。
人はリスクを直感的、感情的に捉えるため、何が怖いかはそれぞれで異なります。こうした多様なリスク認知が存在する社会において、リスク評価、つまりリスクをどう捉えるかにそもそも正解はないので、これが正しい答えですと伝えることができません。科学的事実に揺るぎはなく、提供される情報の信頼度は大きく、価値があります。しかし情報がいかに確かなものであっても、受け取る側に理解されなければリスクコミュニケーションは成り立ちません。
科学的事実が社会にきちんと理解されるにはどうしたらよいか —— 。リスクコミュニケーションは試行錯誤しながらこの命題に挑んできました。こうしてリスクコミュニケーションの概念は、時代とともにステップアップしています。最新のフェーズは、「相手をパートナーとして扱う」というものです(〈リスクコミュニケーションは科学者と市民の「対話」〉参照)。
科学者も誤ることはあります。しかし信頼されていれば、「あの科学者の言うことなら、間違っても受け入れられる」となるでしょう。このように科学者と市民がいわば「パートナー」のような信頼関係になれるかどうかが、リスクコミュニケーションを成功に導く重要なカギとされています。
住民と接し、一つずつ質問に答えるという丁寧な対話を積み重ねてきた神谷氏は、信頼は時間をかけた対話から生まれてくる、と言います。
ナイチンゲールの教えが約160年経た今も機能しているという事実は、ナイチンゲールが普遍的に信頼されていることを表しているにほかなりません。対話だけでなく、活字を通じて築かれる信頼関係もありえるのです。