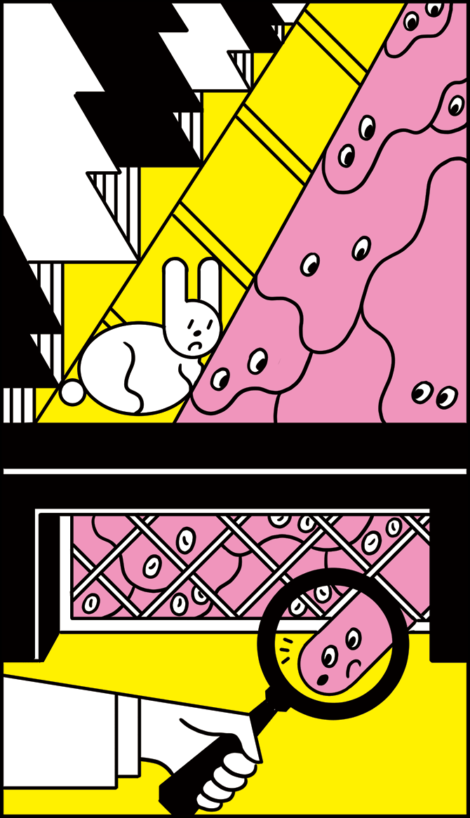
2003年、ヒトゲノム計画の解読が完了し、次世代シークエンサーが登場した。一気に「遺伝子の時代」となったかのように見えた反面、解明が進むにつれ、かえって遺伝子というものの不確かさも明らかになってくるのではないか―。そうした2020年代の「細胞」研究と「遺伝子」研究の相克を、さまざまな観点から追う新連載。第1回は、筆者自身の問題でもあった「出生前診断」をテーマにスタートする。
イラストレーション/北澤平祐
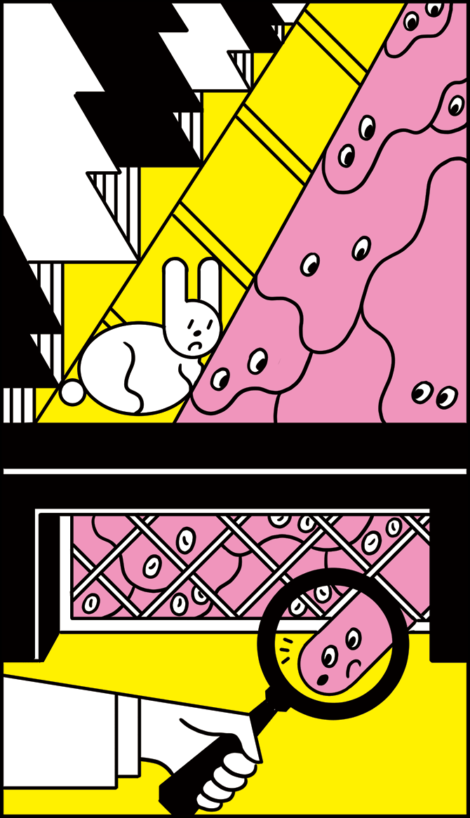
2003年、ヒトゲノム計画の解読が完了し、次世代シークエンサーが登場した。一気に「遺伝子の時代」となったかのように見えた反面、解明が進むにつれ、かえって遺伝子というものの不確かさも明らかになってくるのではないか―。そうした2020年代の「細胞」研究と「遺伝子」研究の相克を、さまざまな観点から追う新連載。第1回は、筆者自身の問題でもあった「出生前診断」をテーマにスタートする。
知ることが必ずしも善ではないのと同様に、知らないでいるのも良いことばかりとは限らない。
2011年、私は無知な妊婦であった。妊娠すればだいたいは健康な子どもが生まれると思っていたのだ。定期的に行く妊婦健診は、胎児の成長を確かめる場であり、妊婦自身の健康管理の場だと捉えていた。自宅で流れていたテレビに目をやると、CNNでは「妊婦の血液から胎児の疾患がわかる技術が実用化された」というニュースがレポートされていた。自分とは関係ない他国の最新技術であり、たいした興味も持たずにテレビを消した。
だが、その数日後に私は病院の診察室で青ざめながら、「母体の血液で胎児の異常が検査できる技術があるというニュースを見たのですが、日本ではできますか」と尋ねていた。いつも通りの、確認だけのはずの健診で告げられたのは、胎児の首の後ろに浮腫があり、ダウン症の可能性もあるということだった。
妊娠にまつわることは考える時間が驚くほど短い。胎児はどんどん成長していき、検査のできる期間は限定されている。私は一日中インターネットを検索し、CNNで見た血液の検査はまだ日本では行われておらず、かわりに母体血による検査ではあるけれども疾患の確率が示される「クアトロテスト」が選択肢としてあることを知った。確率なんてどう判断すればいいかわからない。71分の1は安心できるのか? では142分の1は? 結局、私は知ることを選ばずに、つまり検査は受けずに出産した。
アメリカで始まった新しい検査は、子どもが1歳になる頃には日本で臨床研究として開始され、新型出生前診断(NIPT:Non-invasive Prenatal Genetic Testing)と呼ばれ、急速に広まっていった。2018年の全世界の出生数は1億4000万人だが、イルミナ社の推計では世界で1000万人の妊婦がNIPTを受けたという。
NIPTとは、妊婦の血液中に浮遊する胎児由来のDNAの断片を集め、ダウン症などの染色体異常を調べる検査である。陽性的中率は99%を超える高精度な検査となっている。そして世界に普及したのは非侵襲的であり、妊娠の早期に検査できるという理由もあろう。
それでもなお、NIPTで陽性になった場合は、確定検査として羊水検査を受けなければならない。羊水検査とは、妊婦の腹部に針を刺して、子宮の羊水中に含まれる胎児の細胞を取り出し、染色体やDNAを調べる検査である。こちらは正確性が高いが、デメリットもある。おなかに針を刺すために0.3%程度の割合で流産が起きる。また、羊水を採取できる期間は妊娠15週以降であり、NIPTを受けた後に数週間待つ時間が必要で、さらに羊水検査の結果が出るまでには2~4週間かかる。もしも中絶を選択した場合は、人工的に陣痛を起こして「出産」する「中期中絶」となり、死産届も必要となる。
ではなぜ高精度なのにもかかわらず、NIPTは確定診断にならないのだろうか。それはNIPTで調べられるのは胎盤由来のDNAで、胎児そのもののDNAではないからである。胎児に染色体異常があっても胎盤に異常がない場合もあれば、逆に胎盤に異常があっても胎児は正常であるモザイクの場合も存在する。
それを解決するために、胎盤ではなく、胎児のDNAを調べることができれば確定診断になるという研究も行われているが、一足飛びに胎児の細胞そのものを直接取り出すことができれば、それだけで確定診断であるNIPD(Non-invasive Prenatal Genetic Diagnosis)になるであろう。細胞の中にDNAがセットで入っているため、浮遊する断片よりもさらに正確な検査ができる。
胎児由来のDNAから細胞そのものへ——。この検査で画期的な研究開発を行っているのがTL Genomicsの久保知大氏である。久保氏は中小機構の多摩小金井ベンチャーポートに研究所を構え、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の研究開発型ベンチャー支援事業の最初期の支援を受けて起業した。
「胎児細胞を使えば非侵襲的に、羊水検査に匹敵する確定検査ができます。母体の血液中に胎児の細胞があるということは、NIPTが実用化されるよりずっと前からわかっており、研究の歴史は古いのです」
母体血中に胎児の細胞が存在することは、もともとY染色体を持つ男児の細胞が母体血から見つかったことにより知られていた。だが、胎児の細胞は大変希少のために、どのようにして取り出すかが課題であった。それはチャレンジと失敗の歴史でもあった。
2000年代に、アメリカを中心にこの分野に対して多くの研究費が投下された。胎児細胞を認識する抗体を作って、胎児細胞を取り出そうという試みだ。だが、集中的な研究を行ったにもかかわらず、成功しなかったという。
抗体以外にも、例えば画像処理などで胎児細胞の特徴をひろい、一個一個の細胞を回収する「ピッキング」という方法が研究された。しかし、あくまでも研究室の話で、何万人、何十万人の妊婦のための検査という意味で社会実装は現実的ではなかった。
その間に、遺伝子は急激な解明を遂げた。ヒトゲノム計画は2003年に解読が完了し、DNAの塩基配列を網羅的に解析できる次世代シークエンサー(NGS)が登場。それらを使うNIPTは2011年にアメリカで始まり、一気に遺伝子の時代となり、胎児細胞の研究は抜かれていった。
だが、後れを取った胎児細胞研究に、久保氏は新しい手法を用いて解決を提示しようとしている。その新技術が「マイクロ流路デバイス」である。
「このマイクロ流路デバイスには薄い基板上に100本以上の何種類かの細い流路があり、そこに母体血を流すと、小さい細胞ほどより細い流路溝で、大きい細胞はそれよりも太い流路でトラップできるという理屈です。母体血中の胎児の細胞の大きさにうまく合わせたマイクロ流路デバイスを設計することで、胎児の細胞を一気に濃縮できるようになります」
メカニズムは単純だが、その実現にはハイテクが詰まっているのだという。このマイクロ流路デバイスを実用化するためのハードルはいくつかあったが、そのひとつは血液が詰まるという問題を解決することだった。
「専門家であれば『血液が詰まるから無理だ』と皆が口を揃えるでしょう。私は素材・材料の分野についてはまったくの素人だったから試行錯誤できて良かったんだと思います。マイクロ流路デバイスに大量の血液を流す技術を開発し、特許出願できました」
久保氏の会社のスタッフはパートを含めて7人。中心となる研究者は植物分野の出身で、素材・材料を全く知らなかったからこそ先入観を持たずに取り組むことができた。結果、血液が詰まらない新技術を開発し、マイクロ流路デバイスの量産技術にも成功した。
さらに、胎児の細胞を濃縮する上流だけではなく、濃縮後に別の操作を経て単離された胎児細胞の遺伝子の構造異常を検出できる技術も特許出願中である。次世代シークエンサーを使えば全ゲノムが解析できるが、コストは高くなる。しかし、世界中の妊婦に提供するにはコストを抑えなくてはならず、そのため安価にかつ染色体異常を検出する独自の技術を開発した。その技術を使えば、微小欠損のようなゲノムの変化も高感度かつ安価に検出できるという。
ターゲットとする市場は日本だけではなく、全世界を相手に考えている。現在は日本の大手会社と提携し、欧州での実用化を第一に目指す。日本では20万円ほどするNIPTだが、欧米では500ドルほどで可能であり、そのような低価格を実現し、年間100万から200万検体の規模を予定している。検査体制はオートメーション化する予定だ。
久保氏は京都大学理学部を卒業し、同大学院生命科学研究科で博士号を取得。その後、アメリカ・コロンビア大学に留学して遺伝子発現の多様性を生み出す新たな仕組みの研究をしていた。30歳を目前にキャリアチェンジをしてバイオ企業の職に就き、事業開発や知財などの業務経験を積み、35歳のときに自分の会社を起業した。
そのときに、専門ではなかった出生前診断を選んだ理由は何だったのだろうか。そこにはある個人的な出来事があったのだという。
「私には現在子どもがいますが、その子が妻のおなかの中にいるときにNIPTを受けたことがきっかけです。その妊娠の1年ほど前に、妊婦健診で胎児が危険な状態にあることがわかり、泣く泣く命を諦めざるを得ない経験もあり、NIPTの検査結果を待つ2週間はもの凄いストレスでした。このときは陰性の結果でしたが、もし陽性という結果なら、その後羊水検査で結果を確定するまでにさらに1カ月。NIPTを受ける妊婦さんのほとんどは陰性という結果ですが、陽性と判定された妊婦さんはずっとあいまいな状況で待たされ続けることになる。それはつらいだろうなと感じました」
そのつらさを解消できる方法はないだろうかと、それから久保氏は出生前診断のことを勉強した。
「適当な気持ちで検査を受ける妊婦さんなんかいません。皆それぞれの事情を考えながら、ギリギリの選択をしている。倫理問題はあるけれど、必要とされている検査であり、目を背けていたら誰かが解決してくれるものでもない。よりよい検査が登場して社会がそれをどこまで受容していくか、その繰り返しなんだと思いました」
私は2018年に『選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子』という本を出版した。本書はダウン症ではないと羊水検査の結果を告げられたにもかかわらず、生まれた子はダウン症だったために、医師の誤診を訴えた女性の苦悩を追ったノンフィクションである。そのなかに、もしもダウン症だとあらかじめわかっていたら中絶していたかどうかを裁判で問われる場面がある。その女性は、裁判戦略上は「中絶していた」と言ったほうが有利であったにもかかわらず、どうしてもそう言い切れなかった。そして、「人が命に関わる決断をする時には、崖に指一本でつかまっているところで行うようなギリギリの選択で、その場に立たないと答えはわからない」と述べた。
NIPTが爆発的に広がっているのは、採血だけで検査できる非侵襲性という面が大きい。もしもNIPTのように非侵襲で安全な確定検査がすぐにできれば、妊婦にとっても大きなメリットがあると久保氏は考えた。
「日本は倫理問題が非常にセンシティブですが、なかなか議論が進まない現状に一石を投じ、倫理問題に真正面から挑むベンチャー企業があってもいいのではないかと思いました。倫理問題は静的なものではなく、もっと動的なものだと思います。新しい技術を提示しても、必ずしもその技術を使う必要はない。だけど議論する間隔とスピードを加速させるドライバーの役目になれればと思います」
胎児細胞を調べるNIPDでは、微小欠損症候群や単一遺伝子疾患などの検査も可能となる。そうなると、何が「重篤な疾患」なのか、どのような疾患は調べ、どのような疾患は調べるべきではないのかの線引きがより難しくなってくる。1999年に厚生科学審議会の部会によって出された母体血清マーカーについての見解では、「医師が妊婦に対して、本検査の情報を積極的に知らせる必要はない」としている。それから20年以上が経ち、妊婦が得ることのできる情報も変わり、検査でわかることも増えている。
「妊婦さんにどの情報を伝えるべきかという議論は、新しい技術が出てくるからこそ進んでいくのではないでしょうか。この検査を無理やりマーケティングで普及させていくのではなく、社会の議論と一緒に歩んでいきたいです」
そして遺伝子と病気の解明が進むと、かえって遺伝子というものの不確かさが明らかになるのではないかという。
「DNA上に異常があっても、必ずしも症状が出るとは限りません。特定の構造異常と病気には100%の因果関係があるわけではないのです。例えば、新宿で100人の遺伝子を調べたら、ピンピン元気にしている人でも遺伝子に重大な異常が見つかるなんていうことは決してありえない話ではありません。けれども、妊婦さんに異常を伝えると、『そうはいっても障害児が生まれる可能性があるのでしょう』と思われてしまう恐れもあります」
久保氏は、だからこそ研究を進めないといけないのだと話す。
「DNA上の異常については、これは患者に告知していくべきで、これはレポートすべきではないということがもっと研究・議論されなければならない分野です」
遺伝というと優生や差別につながる印象を持つ傾向もあるが、実はそうではないという。
「出生前診断というと、特定の疾患を絶滅させる優生思想的な言説がありますが、そうではないと思います。NIPTだけを、2010年代の一瞬だけを切り取るとそういう側面はあるかもしれませんが、胎児細胞ベースでいろいろな疾患を見られるようになると、もっと多様な遺伝の姿が見えてくると思います。DNAの異常が疾患にどう結び付くかもっと研究をしてみると、皆がどこか異常で、症状も出たり出なかったりすることがわかってくるのではないでしょうか。例えば自信を持った性格の人もいれば、きれい好きな性格の人もいる。平均的な人ばかりではないからこそ面白い。そしてこのような多様性こそが社会なのではないでしょうか」
出生前診断は後ろめたいものだと考える妊婦も少なくない。だが久保氏によれば良い面もあるのだという。
「個人的な経験を踏まえて考えると、障害について考えるきっかけになりました。遺伝性の疾患だけではなく、交通事故で障害が残ることもあります。最新の技術で、できることがあればやっておいて、生まれるときは受け入れるという妊婦さんが多いと思います。技術は何も使わないというのもひとつの考え方ですし、技術で見られることは知りたいという考えの人もいるでしょう。ですが、どれだけ技術が発達しようとも調べられることは限られている。そして障害は誰の身にも起こりうる。だから障害を差別することなく皆で支えることがあるべき社会の姿なんだということは、この仕事をしているからこそ知ったことだと感じています」
どのような物事にも善悪の両面が必ずある。この連載では善悪を超えた先にある地平を見てみたい。