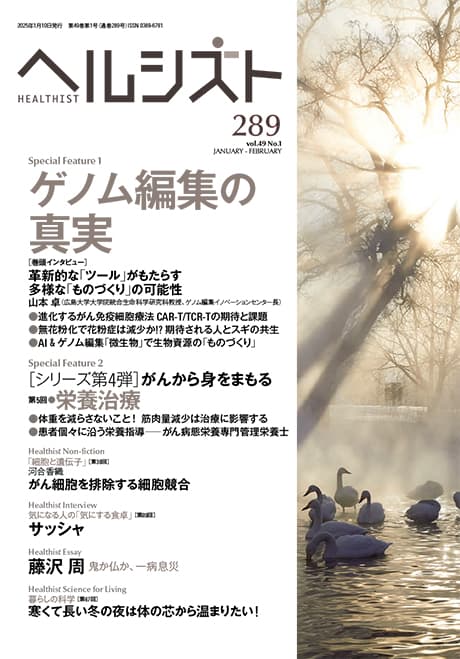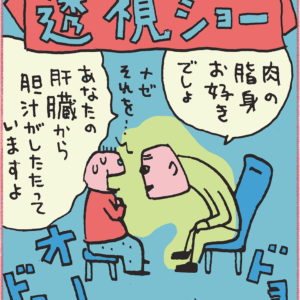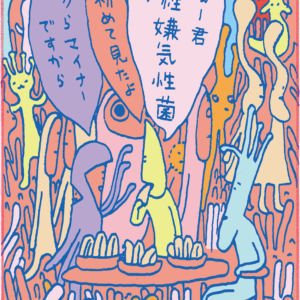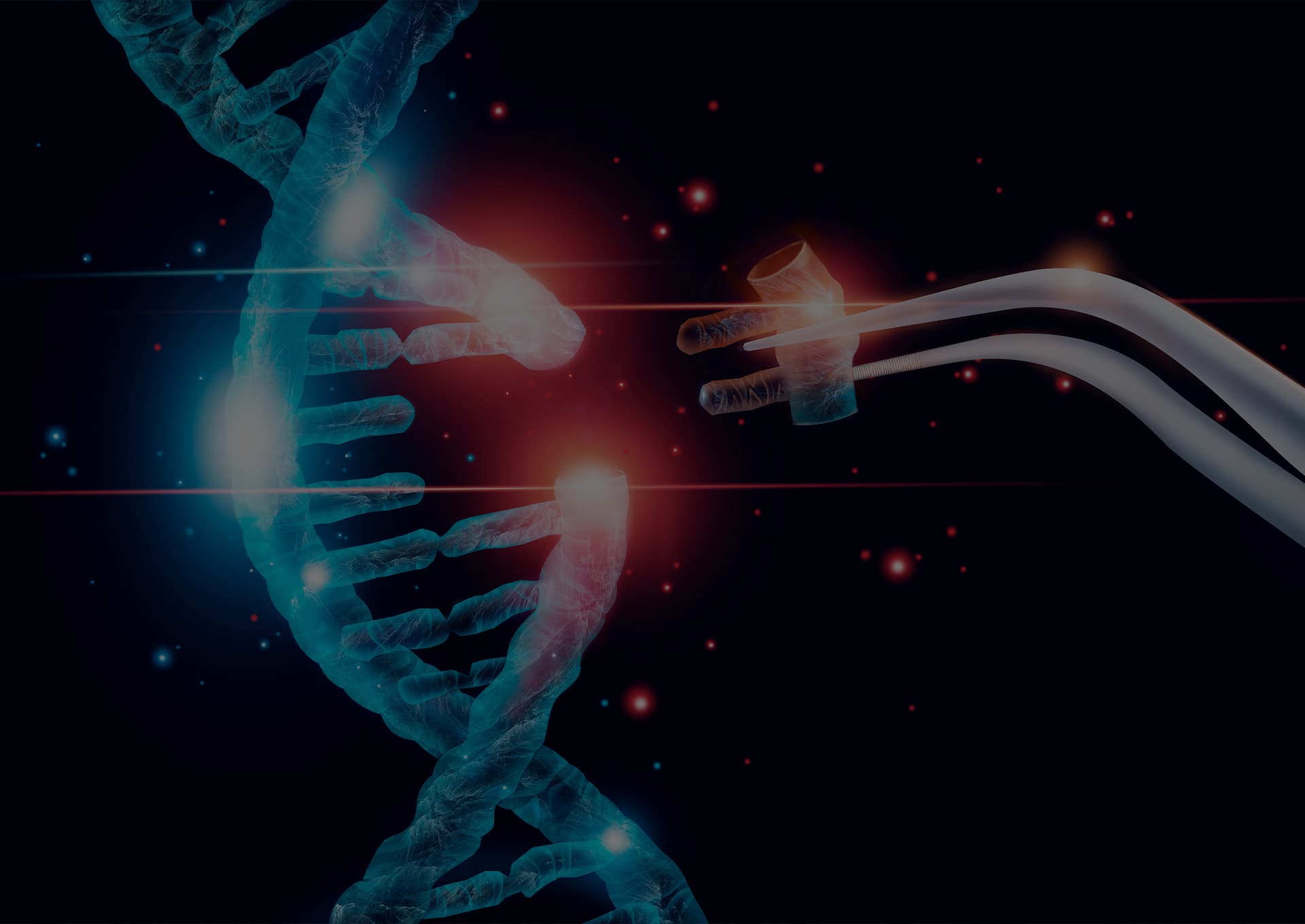細菌のサイズは、通常1~2μ(μ=1000分の1㎜)であり、そのままでは目には見えない。そこで、顕微鏡を使って、数百倍から1000倍に拡大して観察する。オランダのアントニ・ファン・レーウェンフック(1632〜1723年)は、自作の顕微鏡を用いて環境中の微生物を観察した。彼は在住のオランダ・デルフト市において市井のマニアとして、微生物の顕微鏡観察にいそしんでいたようである。観察された微小な物体を「微小動物(animalcule)」と命名していたことから、微生物の第1発見者といわれている。その緻密な観察結果を英国の王立協会に報告し、会員として迎えられている。レーウェンフックは「微生物学の父」とも呼ばれているように、微生物学研究の基本である、対象を観察することのパイオニアである。ちなみに、レーウェンフックは、同時代のバロック絵画の巨匠として知られているヨハネス・フェルメール(1632〜1675年)の死後、地元のデルフト市からフェルメールの遺産管財人として指名されている。
さまざまな色素で微生物を染めて顕微鏡観察すると、菌形は丸かったり(球菌)、桿状(桿菌)であったりする。ハンス・クリスチャン・ヨアキム・グラム(1853〜1938年)により1884年に発表された「グラム染色」法による染色性(クリスタルバイオレットにより紫に染まる場合を陽性、サフラニンを使う対比染色により赤色に染まる場合を陰性)は、現在でも細菌の基本同定のよすがとなっている。その他にも、細菌の独特の構造や構成成分に応じたさまざまな染色法(抗酸菌染色、莢膜染色、芽胞染色など)があり、病原微生物の同定に役立っている。
臨床医療機関との共同研究の過程で、消化器内科のH先生から、「腸内細菌叢の研究材料は新鮮便を対象とすることが多いが、これでは腸管粘膜や粘液層に生息する菌群を逃してしまっているのではないか? 腸管壁内面に局在する細菌叢を正確に観察する方法はないのか?」と問われた。そこで、蛍光 in situ ハイブリダイゼーション(FISH)法(微生物の形態を保持した状態で、その核酸の特定部位に相補的な蛍光標識プローブを当てて微生物を検出する手法)を応用した、「多重染色FISH」法を開発した。この方法は、便微生物を塗抹したスライドガラスに、蛍光色素を結合させたオリゴDNAプローブ(蛍光DNA-P)を反応させて、これを蛍光顕微鏡で観察すると、対象とする微生物のみが蛍光を呈して検出される、というものである。当時、研究をリードしたT研究員が、お互いに重ならない波長(励起および蛍光波長)を有する3種類の蛍光色素(FITC、Cy、TAMRA)をDNA-Pの5’末端あるいは3’末端に結合させることにより、1つの塗抹サンプルを7種類(単独:3、異なる2種:3、3種:1)に染め分ける多重染色FISH法を確立した。さらにT研究員は、スライドガラスに張り付けた腸管粘膜組織の薄切切片についても、スライドガラスへの固定方法を工夫することで、腸管上皮の粘液組織を失うことなく、多重染色FISH法を用いて腸管粘膜や粘液内の腸内細菌の局在を明確に観察する方法を完成させ、H先生の要望に応えることができた。
現在では、電子顕微鏡(拡大倍率が数万倍、走査型電顕による立体的な画像観察、および透過型電顕による菌体断面観察)、共焦点レーザー顕微鏡(厚さを持った検体の異なる位相の観察により3次元情報を得る)、および静止画像のみでなく動画による観察など、多様な微生物観察が可能となっている。さらに、ハードウェアの進歩により、直接にレンズをのぞき込む従来の鏡検はもとより、画像取得のためのカメラ操作も適宜機械任せで、取得されたカメラ画像をPC画面で観察するようになった。対物レンズ操作によるピント合わせなども自動となり、重宝している。
- *1 天児和暢. レーウェンフックの微生物観察記録. 日本細菌学雑誌, 69: 315–330, 2014.
- *2 Bartholomew JW, Mittwer T. The Gram stain. Bacteriol Rev, 16: 1–29, 1952. doi: 10.1128/br.16.1.1–29.1952.
- *3 Takada T, Matsumoto K, Nomoto K. Development of multi-color FISH method for analysis of seven Bifidobacterium species in human feces. J Microbiol Methods, 58: 413–421, 2004. doi: 10.1016/j.mimet.2004.05.006.
- *4 高田敏彦, 角将一, 野本康二. 多重染色FISH法による腸内フローラ解析. 腸内細菌学雑誌, 29: 123–134, 2015.